核燃料サイクル
「核燃料サイクルの本当の話をしよう」澤井正子 岩波「科学」2014年5月号(岩波書店許諾)
核燃料サイクルの
本当の話をしよう
原子力資料情報室
澤井正子(さわい まさこ)
「エネルギー基本計画」が
創造する
新たな“神話”:
準国産エネルギー
安倍政権が4月に決定した「エネルギー基本計画」では,原子力発電を以下のように位置づけている。
「燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく,数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる準国産エネルギー源として,優れた安定供給性と効率性を有しており,運転コストが低廉で変動も少なく,運転時には温室効果ガスの排出もないことから,安全性の確保を大前提に,エネルギー供給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源である。」
この一段落で一文の長文の意を,即座に正確に理解することは容易ではない。特にわからないのは,「数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる準国産エネルギー源」というくだりである。
「準国産エネルギー」とは?かつてそれはプルトニウムをさして使われていた。ところが今は違うらしい。東京電力のウェブサイトでは,
「この(核燃料)サイクルが確立すると,ウランやプルトニウムは,国産のエネルギー資源みたいに使うことができます。そのために,ウランやプルトニウムを準国産エネルギーというのです。」
とある。全量輸入されているウランは,石油や石炭と同じように外国産のエネルギー源なのでは?「このサイクルが確立すると」と東京電力も断っているように,確立できていないのだから,やはり準国産とは言えないはず。昔は,原子力発電によるウランの核分裂反応の結果,副産物として原子炉内に生じるプルトニウムを「準国産エネルギー」と言っていた。ところが,いつのまにかウランまで「準国産」になっている。
一方,「数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる」というのは,もっとわからない。核燃料はなるほど3~4年原子炉に装荷されている。しかし実際は,燃料の1/3~1/4を新燃料に毎年交換しており,5%以下の濃縮度で燃料の取り替えなしで数年運転するのは実際は無理だろう。
原子力発電が「優れた安定供給性と効率性を有しており,重要なベースロード電源」であると述べるために並べられた説明は,東京電力福島第一原発事故によって崩壊した「安全神話」に代わる,新しい「神話」剏造のための新たな「宣言」ではないか。
「エネルギー基本計画」で「核燃料サイクル政策」については,以下のように記されている。
「我が国は,資源の有効利用,高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から,使用済燃料を再処理し,回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としている。」
「具体的には,安全確保を大前提に,プルサーマルの推進,六ヶ所再処理工場の竣工,MOX燃料加工工場の建設,むつ中間貯蔵施設の竣工等を進める。また,平和利用を大前提に,核不拡散へ貢献し,国際的な理解を得ながら取組を着実に進めるため,利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持する。」
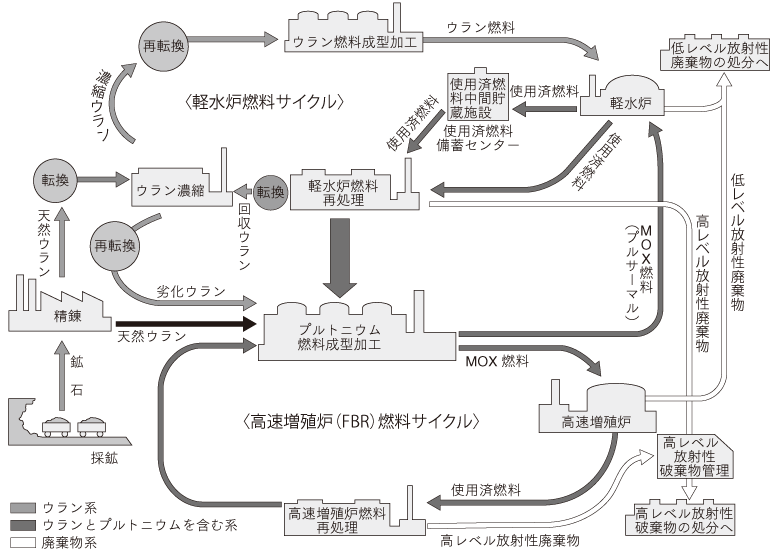
図1―核燃料サイクルの説明図(電気事業連合会ホームページ掲載の図より作成。現在は高速増殖炉「もんじゅ」のない図に替わっている)
高速増殖炉原型炉「もんじゅ」はナトリウム漏れ事故(1995年)をはじめトラブル続きで,現在はおよそ1万カ所の点検漏れにより運転停止(試験運転再開準備の停止)を命じられている。軽水炉燃料サイクルについては,使用済み燃料再処理を担う六ヶ所工場も(廃棄物処理のガラス固化工程がうまくいかず)運転していない。MOX燃料は,外国に委託したものが送られてきているだけである。
核燃料サイクルとは
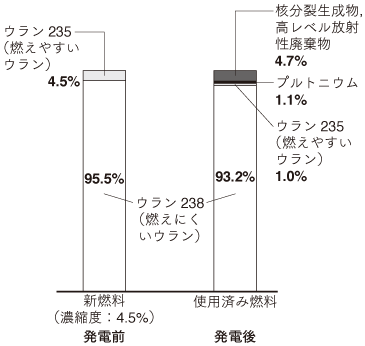
核燃料サイクルと再処理について,いま一度考えてみよう。図1は「核燃料サイクル」を説明するのにしばしば使用される図である(が,「軽水炉サイクル」と「高速増殖炉サイクル」がはっきりと記されている図は最近は珍しい。高速増殖炉「もんじゅ」の計画が事実上破綻してからは,高速増殖炉が記載されていない図がとても多い)。
ウランは,エネルギー資源とするためには非常に手間のかかる物質である。石油や石炭,天然ガスとくらべると,核燃料として原子炉に装荷されるまでに多数の作業工程が必須となる。ウラン鉱山での採鉱から始まって,精錬,転換,濃縮(原子炉で反応させるウラン235の比率を高める),再転換,核燃料への成型加工,そして原子炉への装荷,使用済み燃料(放射性廃棄物)へと,その形状を変えていく。この流れ全体が「核燃料サイクル」と一般的には呼ばれている(ただし,「サイクル」と呼ばれるようには「循環」していないことは,後に詳述する)。
ウランをオーストラリアで採掘し,アメリカで濃縮,加工するというように,燃料製造過程は世界的な規模で展開しており,各工程間の輸送や濃縮には相当なエネルギーを消費する。さらに発電後に生じる高レベル放射性廃棄物の処分はもっと困難な作業で,いまだに処分場を確定した国はない。原子力発電は,燃料製造から廃棄物処理までのシステム全体を前提にしなければ成り立たない。
原子力発電は,ウランの核分裂によって発生するエネルギーを発電に利用しているが,その際,原子炉の中で副産物としてプルトニウムという核物質が生成される。図2はウラン燃料の組成変化の一例を示している。濃縮度4.5%(ウラン235の存在比)の新燃料の場合,ウラン235が4.5%,ウラン238が残りの95.5%となる。これが原子炉での発電後には,核分裂生成物や高レベル放射性廃棄物が約5%,新たに生成されたプルトニウムが約1%,残りはウランの235と238で約94%となる。ウランもプルトニウムも使用済み燃料として原子炉から取り出され,ワンススルー(直接処分)政策の国(アメリカ・カナダ・スウェーデン・フィンランドなど)は使用済み燃料がそのまま高レベル放射性廃棄物となる。使用済み燃料中のプルトニウムをさらに利用することを考えている場合は,使用済み燃料を冷却後に再処理し,MOX燃料(プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料)への加工と移行していく。
原子力発電所の使用済み燃料を再処理し,取り出したプルトニウムを再利用しようとする(つまり核燃料サイクルを「閉じる」)考え方が「核燃料サイクル政策」といわれるものである。この再利用は,高速増殖炉が稼働し,プルトニウムを燃料として一定量以上必要とし,サイクル=循環を連続的に行うことによってはじめて意味をもつ。日本は1970年代以降,「核燃料サイクルの確立」を目指して開発してきたが,完全に頓挫している。高速増殖炉も,再処理工場も,目標年である2000年をとうに過ぎてもいまだに稼働できない。
計画の破綻を取り繕うために,余剰プルトニウム対策として,「プルサーマル(軽水炉でのMOX燃料利用)」や再処理できない使用済み燃料のための「むつ中間貯蔵施設」の建設を推進しなければならないのが実情である。
再処理工場の工程
「核燃料サイクル」の本来の目的である高速増殖炉でのプルトニウムの増殖が頓挫しても,再処理工場の建設計画を巨大な公共事業として位置づけるため,最近打ち出されているポイントが,「資源の有効利用,高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等」である。まるで一般ゴミの「3R(Reduce・Reuse・Recycle)」のような話だ。再処理はそれほど環境に「やさしい」技術なのだろうか。
再処理工場の仕組みについて,六ヶ所再処理工場を例に概要を見てみよう(図3)。
原子炉から取り出された使用済み燃料は(ある程度放射能を減衰(冷却)させてから)
→[貯蔵・冷却]六ヶ所再処理工場では,原発から輸送された使用済み燃料をさらに冷却
→[剪断]使用済み燃料を切り刻む
→[溶解]剪断片を濃硝酸に溶かす
→[分離]高レベル廃棄物(死の灰)を分離する
└→[高レベルガラス固化]分離工程で分かれた高レベル放射性廃棄物をガラス成分と混ぜ,ステンレス・キャニスターで冷却・貯蔵する
→[精製]ウランとプルトニウムを分離する
→[脱硝]ウラン溶液,プルトニウム溶液から硝酸を抜く
→[貯蔵]ウラン酸化物,およびプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX粉末)として貯蔵(六ヶ所再処理工場のプルトニウムは,日米原子力協定の規定により,プルトニウム単体ではなくウランとの混合酸化物(MOX粉末・プルトニウム50%:ウラン50%)として回収される。)
再処理工場は,使用済み燃料に含まれるウラン,プルトニウム,核分裂生成物(死の灰)に分離する化学工場である。巨大な放射能の塊である使用済み燃料を濃硝酸,リン酸トリブチル(TBP),ノルマル―ドデカン(n-Dodecane),など多種・多様な化学溶媒を使用して化学的に分離する。そのため,火災・爆発・腐食・臨界・漏洩・汚染・被ばく・テロなど,化学工場と原子力施設の両者の危険性をあわせもつことになる。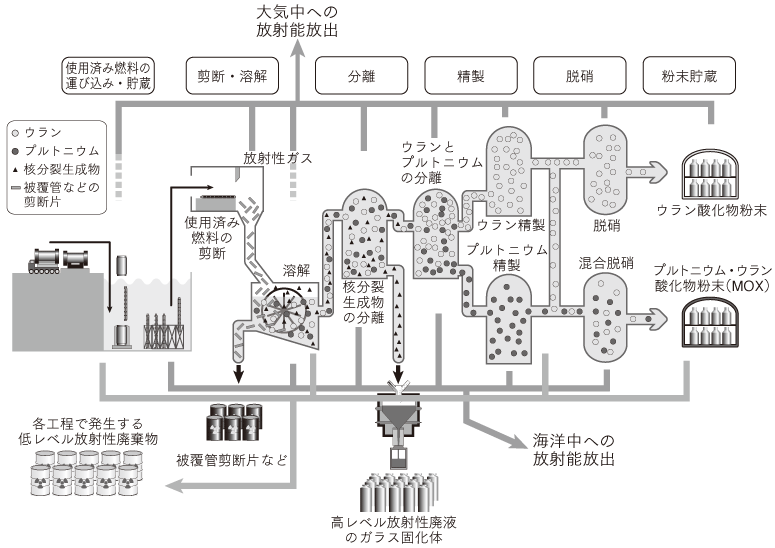
図3―六ヶ所再処理工場工程の概要
原子力資料情報室作成。
夢のリサイクルの現実
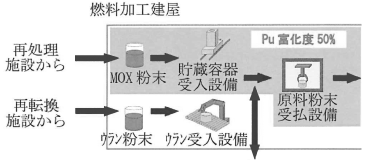
出典は脚注2参照。
「核燃料サイクル」の最大の売りは,「リサイクル」だろう。「使用済み燃料を再処理し,取り出したウランとプルトニウムをすべて再利用できる」という主張がなされる。六ヶ所再処理工場では,使用済み燃料が最終的にはウラン酸化物,プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX粉末),そしてガラス固化体という形態になる。政府や事業者の説明では,ウラン,プルトニウム(MOX粉末)はリサイクルされ,高レベル放射性廃棄物は約50年の貯蔵後,最終処分場へ搬出されることになっている。
核燃料サイクルの最大の目的は,原子炉でウランが燃えることにともなって生じるプルトニウムの利用である。使用済み燃料中に1%残っているプルトニウムを再び核燃料に加工するために,現在,六ヶ所再処理工場のプルトニウム(MOX粉末)貯蔵建屋のすぐ南側に,MOX燃料加工工場(130t-HM(トン―重金属換算)/年)が建設中である。両施設は地下トンネルで結ばれており,プルトニウムが輸送される。当然MOX燃料に利用されるウランも再処理工場から輸送するものと思われるだろうが,実態はそうなっていない。これは日本原燃自身が作成した資料―「MOX燃料加工施設 加工事業変更許可申請の概要について」https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10317940/www.nsr.go.jp/data/000036188.pdf(p.4)より―
に非常に明快に示されている。図4は六ヶ所MOX燃料工場の製造工程の概要の一部だ。
いわゆるプルサーマル燃料(1/3MOX燃料)は,燃料集合体平均でプルトニウムが約5%,ウランが95%の組成である。六ヶ所再処理工場のMOX粉末はプルトニウム50%,ウラン50%でプルトニウムの濃度が高すぎるので,このMOX粉末にウランをまぜてプルトニウムの濃度をさげる必要がある。材料の搬入先として,日本原燃の資料は,プルトニウム(MOX粉末)は「再処理施設から」,ウランは「再転換施設から」としている。再処理工場からではない。「再転換」とは六フッ化ウランの再転換を意味していて,MOX燃料製造に新たに利用されるウランは,六ヶ所ウラン濃縮施設に貯蔵されている劣化ウラン(ウラン238が約99.9%)を再転換して利用する計画なのである。つまり,日本原燃自身にも,六ヶ所再処理工場の回収ウランを使用する予定はまったくない。それは再処理回収ウランが,核燃料とするにはとても扱いにくいためだ。
ウランは原子炉で核分裂することでアイソトープ(放射性同位体)が増える。天然に存在する同位体はウラン234,ウラン235,ウラン238であるが,原子炉での燃焼(核分裂)によってウラン232,ウラン236が生成される。
ウラン232は,天然ウランには含まれない核種で,半減期が短く,娘核種として高放射線核種(タリウム208,ビスマス232)を生成し強いガンマ線を放出する。そのため,再処理工場でつくられる回収ウランの放射線量が非常に高くなる。一方,ウラン236は,中性子を吸収しやすく核分裂を阻害する。また,回収ウランは再処理で分離しきれなかったプルトニウム,ウラン,核分裂生成物や超ウラン元素も含んでいる。
再処理回収ウランを再利用して再濃縮や成型加工を行おうとすると,労働者の被曝対策や遮蔽,閉じ込め機能の強化が必要で手間とコストがかかり,世界的にもほとんど利用されていないのが実態である。
では英・仏ではどうやってMOX燃料を製造しているのだろうか。扱いにくい再処理回収ウランを無理して利用しなくても,今日まで世界中の原発に燃料を供給してきたウラン濃縮施設には,処分できないほどの「劣化ウラン」が存在している。こちらは放射線の問題もなく,タダ同然で利用できる。日本でもまったく同様である。
「核燃料サイクル」における再処理回収ウランには,まったく出番はない。これが使用済み燃料中に約95%も存在するウランの実の姿だ。(唯一使用が確認されているのは,兵器としての「劣化ウラン弾」である。)
しかし政府や事業者も「使用済み燃料のリサイクル」を謳うからには,少しでもリサイクルの実績を作りたい。回収ウランを核燃料として利用された例も非常にわずかだがある。それが表1だ。最大に利用した1995年でも美浜原発の約20tU(トン―ウラン換算)である。日本全体で毎年原子炉に装荷される約1000tUの新燃料に対する割合は,0.02%。リサイクルに値するようなものではない。
六ヶ所再処理工場では年間処理量約800tUに対して,プルトニウムは約8t,回収ウランは約740tUである。再処理とは,ほとんどウランを回収する作業なのだ。しかし94%という膨大な量の再処理回収ウランに使途はなく,何の役にも立たない。その言い訳として政府は,「将来のウラン需要に備えた戦略的備蓄」と言いつくろい,永久貯蔵という実態を隠している。日本が所有している回収ウランはすでに約7000tUで,東海再処理工場(500t)以外は,フランスのラ・アーグ再処理工場,イギリスのソープ再処理工場など海外でただ貯蔵されている。海外委託再処理の総量は約7100tであり,ほとんどリサイクルなどできていない実態は明らかだ。これが「使用済み燃料のリサイクル」の実像である。正確には,「1%のプルトニウム・リサイクル」であるが,それも高速増殖炉もんじゅ計画の頓挫によって,実現できないことはすでに衆知の事実である。現実を見れば,「使用済み燃料のリサイクル」というような宣伝は,ほとんど国家的詐欺に等しいと言えるのではないだろうか。
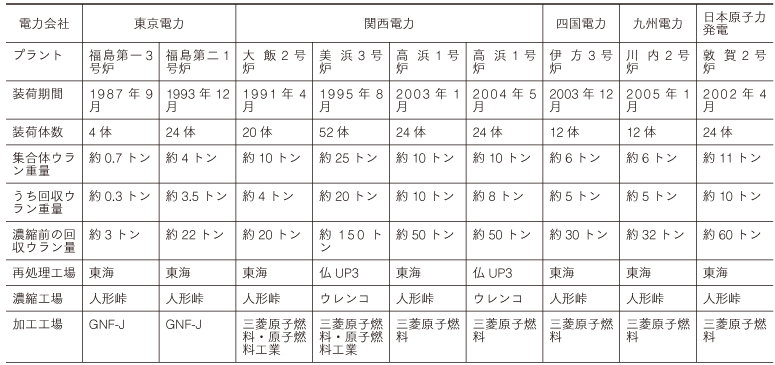
表1―再処理回収ウランの利用状況
動燃人形峠事業所 (当時)のウラン濃縮原型プラントにおける回収ウランの濃縮は,1996年9月~97年5月,97年12月~98年3月 の2回,「回収ウラン再濃縮実用化試験」としておこなわれた。 (福島瑞穂参議院議員の資料請求に対する資源エネルギー庁の回答に一部加筆)
再処理は廃棄物の量を減らす?
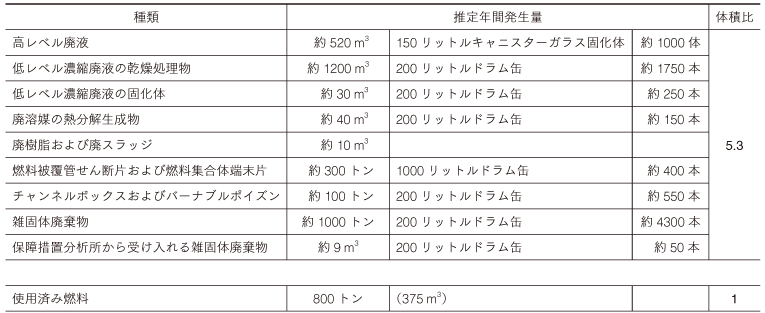
表2―六ヶ所再処理工場の固体廃棄物の推定年間発生量(800 tU/年)
高レベル廃液は,高レベル濃縮廃液,不溶解残渣廃液,アルカリ濃縮廃液,アルカリ洗浄廃液である。 六ヶ所再処理事業所・事業許可申請書(補正)をもとに原子力資料情報室作成
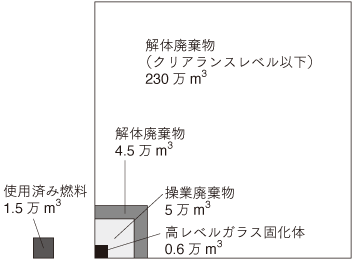
40年運転,3.2万トンの使用済み燃料を処理。電気事業連合会の試算(総合資源エネルギー調査会電気事業分科会コスト等検 討小委員会資料)をもとに原子力資料情報室作成。
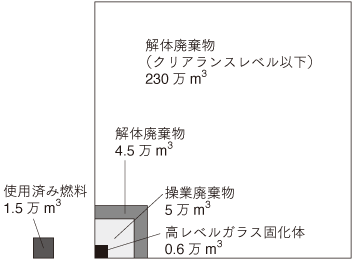
40年運転,3.2万トンの使用済み燃料を処理。電気事業連合会の試算(総合資源エネルギー調査会電気事業分科会コスト等検 討小委員会資料)をもとに原子力資料情報室作成。
次に“Reduce”である。使用済み燃料を再処理することによって高レベル放射性廃棄物が減容化され,有害度が低減されるという,まるで環境に対して大きな利点があるような主張である。
高レベル放射性廃棄物は,再処理工場ではガラス固化体に製造される。なるほど,BNFL(英国核燃料会社)もCOGEMA(仏の核燃料企業)も,再処理で生じる高レベル廃棄物の量を減らすことに多大の投資をしてきた。よく言われるのは使用済み燃料とガラス固化体の体積の比較であり,体積比だけをみれば1/4になるかもしれない。しかしこれは比較できないもの同士を比べていて,およそ科学的議論とは言えないだろう。前項でも明らかにしているが,使用済み燃料には,94%のウラン,1%のプルトニウム,そして5%の高レベル放射性廃棄物が含まれる。一方のガラス固化体には4%の高レベル放射性廃棄物しか含まれていない。使用済み燃料中の95%は分離されて,別の場所に貯蔵されているだけだ。たとえガラス固化体を地層処分できたとしても,地上に残された膨大な回収ウランはどうなるのだろうか。こんな不公平な比較は,子どもでもおかしいと気づくだろう。
むしろこの減容化議論で問題なのは,再処理に伴って必ず発生する大量の中・低レベル廃棄物について徹底的に無視していることではないだろうか。表2は六ヶ所再処理工場が1年間操業した場合に発生すると考えられている放射性廃棄物について,事業許可申請書から抜き出したものだ。高レベル廃液から低レベルのものまで,事故もなく計画どおり運転された場合が試算されている。これらの放射性廃棄物を150リットルガラス固化体や200リットルドラム缶の体積で合計したものと使用済み燃料を1として比べると,5.3:1となる。六ヶ所再処理工場で発生する放射性廃棄物の体積は,元の使用済み燃料の約5倍の量に達する。
しかしこの数値は,現実的な数値とは言えない。現在の六ヶ所再処理工場でのガラス固化体製造試験のトラブルをみても,廃棄物の発生量はこのような推定量では到底収まらないと考えられる。実際,原子力資料情報室の試算では,東海再処理工場で約16倍(1992年3月までの実績値),ラ・アーグ再処理工場で6.7倍(1990年頃の実績値)となっていて,どこの再処理工場でも放射性廃棄物の量は大幅に増えている。また,表2からも明らかなように,濃度・仕様・形態がさまざまな放射性廃棄物が発生し,最終的処分についても困難性が増すことになる。そして何よりも,これらは再処理を行わなければ発生しない廃棄物だ。
六ヶ所再処理工場は年間800tの処理量で,40年間操業する予定だ。3万2000tの使用済み燃料を再処理し,運転を終え施設が解体されるとどうなるか,廃棄物はどう増えるのか,試算してみたのが図5である。施設は作業員が容易には近づけないほど高濃度に汚染され,操業中の廃棄物が蓄積し,さらに施設の解体廃棄物と解体作業に伴う廃棄物が発生する。使用済み燃料と比してガラス固化体がたとえ小さくなったとしても,発生する放射性廃棄物の総量は150倍以上となる。(不本意ながら)クリアランス制度を導入していわゆる「スソキリ(放射能レベルの低いものを一般産廃として扱うこと)」を実施しても,6倍である。そしてこの施設の解体作業にも,操業期間と同じくらいの年月が必要だというのが日本原燃の説明である。再処理が廃棄物対策として何らかの意味があるとは,到底言えないだろう。
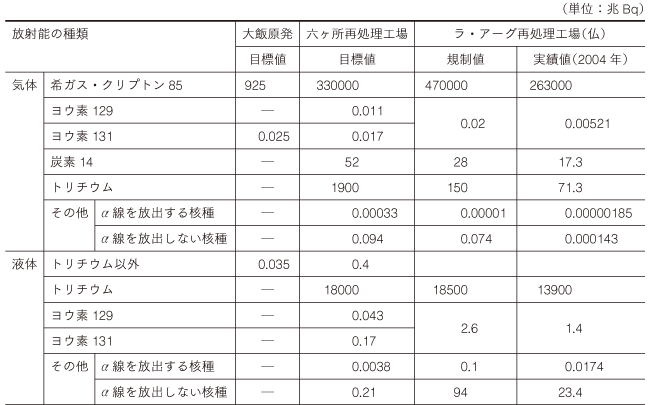
表3―六ヶ所再処理工場の管理目標値
垂れ流しにされる
気体廃棄物と液体廃棄物
再処理工場が環境にやさしくない実態は,別にもありこちらのほうが深刻な問題だ。六ヶ所再処理工場で放射性廃棄物として貯蔵されるものは固体廃棄物のみであり,気体廃棄物,液体廃棄物は,すべて操業中に環境へ放出されることになっている。「放射能の垂れ流し」である。もちろんさまざまな処理やフィルタを通したりするが,後述するようにトリチウム,クリプトンなどは経済的理由で処理施設の設置が見送られた。もともとプルトニウムという軍事物質を分離するための施設である再処理工場では,環境への配慮,被ばく対策など,十分に考慮する対象ではない。
気体廃棄物は,下記のように大気に放出される。
- クリプトン85,炭素14,トリチウム(一部気体廃棄物,大部分は廃液として)は,全量大気中に放出。
- 燃料棒の剪断・溶解によって開放される,クリプトン,キセノン,アルゴンなどの希ガス類,NOx(窒素酸化物),ヨウ素,炭素14などは,高さ150mの主排気塔から大気中に放出。
- 工場の各建屋の塔槽類からの気体性放射能を含む廃ガス類は,洗浄塔,HEPA(高性能粒子)フィルタを通した後,主排気塔または北排気塔(ハル・エンドピースおよびガラス固化体貯蔵建屋換気筒)の排気口から放出。
- ガラス固化施設ガラス溶融炉からの気体性放射能を含む廃ガス類は,洗浄器,ミストフィルタやHEPAフィルタ,ヨウ素フィルタを通した後,主排気筒の排気口から大気中へ放出。
- 汚染の可能性のある区域からの排気は,HEPAフィルタを通した後,主排気塔,北排気塔,低レベル廃棄物処理建屋換気塔の排気口から大気中に排出。汚染の恐れのないものは直接放出。
- ガラス固化体貯蔵施設の冷却空気中の放射化されたアルゴンは,冷却空気出口シャフトから直接大気中に放出。
液体放射性廃棄物については,下記のように海に放出される。
工場内の施設,機器類,蒸発缶などから発生する,廃液,濃縮液などには,トリチウム,ヨウ素,テクネチウム,ルテニウム,ロジウム,コバルト60などの放射化核種,ウラン,ネプツニウム,プルトニウムおよびその他のアクチノイドなどの放射性核種が含まれる。トリチウムは水として廃液中に移行し,捕獲することは不可能であるため,使用済燃料中にある全量を海洋に放出(一部は気体廃棄物)。
これらの廃液は,蒸発処理,熱分解処理,ろ過処理,乾燥処理などが行われる。処理された廃液と処理を必要としない廃液は,液体廃棄物の排気設備の油分除去系または海洋放出管理系へ移送され,放射能の量および濃度を確認した後,六ヶ所工場の沖合い3km(水深44m)に設置された海洋放出管の放出口から海中に放出。
このように大気中,海水中に捨てられる放射能は,廃棄物としてはいっさい管理されない。これが,政府から事業許可を得ている六ヶ所再処理工場の運転方法である。一方気体廃棄物,液体廃棄物の管理目標値は表3のようになっている。原子力発電所と比べて桁違いの放射能が事故ではなく通常運転の状態で環境に放出される。再処理工場のための特別な基準だ。管理目標値は,規制値でも基準値でもなく,この程度には収めたい,という日本原燃の「期待値」である。この数値が達成できなくても,事業許可が取り消しになるようなものではない。このような運転がなぜ許可されるのか,原子炉とくらべても完全なダブルスタンダードである(なぜこのような放出が可能なのかは,次項参照)。
再処理による廃棄物の「減容」の実態など,どこにも見当たらない。わずか1%のプルトニウム・リサイクルのための,合法的な大規模放射能放出が許可されているのだ。
被ばく評価:
22マイクロシーベルトの迷走
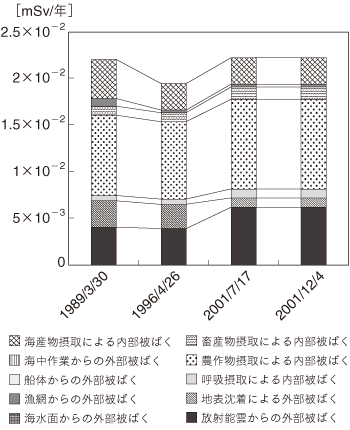
平常時の被ばく(実効線量)の評価
再処理事業指定申請書他から原子力資料情報室作成。
では,放出された放射性廃棄物の住民への影響はどのように評価されているのか。六ヶ所再処理工場は通常運転時でも気体廃棄物,液体廃棄物として大量の放射能を放出するが,住民の被曝量(実効線量)は,年間0.022mSv(22µSv)で「自然放射線の1mSvと比して無視できるほど十分低い」(強調引用者)として許可されている。
一般人(公衆)の線量限度について,ICRP(国際放射線防護委員会)「1990年勧告」では年間1mSv(1000µSv)とされているが,原子力施設に関する法令では,明示的にしめされていない。しかし原子力発電所は多数存在するので,個々の原子力発電所に対しては年間50µSvを被曝の目標値とするよう定められている。さらに原子力発電所が環境に放出する放射性物質に対しては,気体状の放射性廃棄物についても液体状の放射性廃棄物についても濃度規制が課せられる。
一方,六ヶ所再処理工場からの気体廃棄物に対しては,敷地境界外に出るまでの大気中での希釈効果を考慮して,原子力発電所と同等の濃度規制が課せられる。しかし液体放射能,たとえばトリチウムの放出では濃度が高すぎて原子力発電所の規制をクリアすることができない。そのため政府は再処理工場が放出する液体放射能については,六ヶ所住民が村で生活し村の生産物・食品を食べるという仮定で1年間の被曝線量を計算し,その計算値が規制値を下回ればよいとしている(いちばん被曝するのは漁師さんとされている)。日本原燃の被曝評価は,さまざまな仮定に仮定を重ねて,たくさんの係数や計算式,コードなどを使って計算されたものだ。係数がすこし変われば,何桁も数値が違うような場合もある。したがって計算値が2桁の有効数字で示されているが,評価としてはあまり意味がないだろう。
さらに問題は,この「年間22µSv」の計算値は,実は何種類もあることだ(図6)。再処理事業指定申請時(1989(平成元)年3月30日)の実効線量(当量)で22µSv,1996(平成8)年4月26日の変更申請の実効線量(当量)はすこし下がって20µSv,2001(平成13)年7月17日の変更申請は実効線量22µSv,認可された2001(平成13)年12月4日の変更申請は実効線量22µSvと計算されている。数値だけをみると大きな違いはないように見えるが,内訳を見ると,デタラメと言っても過言ではない様相を示している。
一言で22µSvといっても,評価時によって,放射能雲からの外部被ばくが倍近く増加したり,逆に地表沈着による外部被ばくは1/4に減少したり,漁網からの外部被ばくは半減するなど,大きく数値が変動していて,計算によるまさにマジックの様相である。しかし全体の評価は「22µSv」できれいに横並びだ。このような評価は推定計算としてほとんどあり得ない結果であり,信頼することは到底できないだろう。むしろわかりやすい解釈としては,最初に申請時の「22µSv」があり,そこに被曝量をさじ加減で合わせたに過ぎないのではないだろうか。
再処理は廃棄物問題の先送り
核燃料サイクル,特に六ヶ所再処理工場の問題を扱うと必ず出てくる資料が,「各原子力発電所(軽水炉)の使用済み燃料貯蔵状況」である。これには「1炉心」「1取替分」,「管理容量」などが記載され,必ず最後に「管理容量を超過するまでの期間」つまり,「使用済み燃料が滞留して原発の運転ができなくなる期日」が明記されている。
(原子炉の燃料貯蔵プールは,緊急時のために「1炉心+1取替分」を空けておくことが義務づけられている。)
なぜかと言えば,事業者の本音は,「六ヶ所再処理工場でプルトニウムの生産が遅れていて困る」のではなく,「使用済み燃料を原発から出せないから困る」のであろう。問題はプルトニウムではなく,プールである。原発の稼働を続けるためには再処理工場ではなく,そこに併設されている使用済み燃料プールという“ゴミ置き場”を確保したいのだ。
六ヶ所再処理工場の問題を考えてくると,すでに核燃料サイクルはエネルギー問題などではなく,単なる“核のゴミ”問題であることは明らかだ。プルトニウムの増殖という「核燃料サイクル」の目的はすでに頓挫しているにもかかわらず,手段にすぎなかった「核燃料再処理」が国民を欺くような理由をつけて目的化されている。再処理工場には,その建設や運転を正当化できる理由は何もない。むしろ再処理によって核のゴミ問題は先送りされ,廃棄物は増殖し,困難性は増すばかりだ。政府・事業者は「核燃料サイクル政策」の破綻を素直に認め,放射性廃棄物問題について「六ヶ所再処理工場推進」というようなコストのかかる,安易な解決方法を放棄するべきだ。問題は非常にシンプルで,「放射性廃棄物管理・対策」をどうするのか,ということだけを真剣に議論するべき時である。
補論
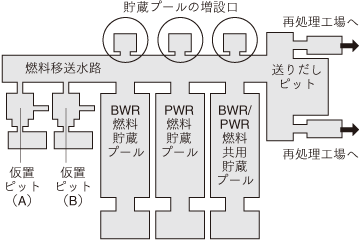
原子力資料情報室作成。
再処理指針現在,新規制基準適合審査が行われている。六ヶ所再処理工場も審査中だが,現行の「新基準」のもととなった「再処理施設安全審査指針(以下「指針」)」の作成過程は,にわかには信じられないような議論によって進められたことが明らかになっている*3。
六ヶ所再処理工場について最初の安全審査が行われたのは,1989年3月末から1992年12月までの期間である。原子力安全委員会は審査の基準となる「指針」を準備するため,当時の核燃料安全基準専門部会とその下に設置された再処理施設小委員会,さらのその下に起草ワーキンググループ,事故評価ワーキンググループなどを設置した。再処理施設小委員会は,1979年6月に第1回会合を,そして1985年10月まで合計22回の会合を非公開で開催した。
1972年にむつ小川原開発が閣議口頭了解されたが,1973年3月に住民はむつ小川原巨大開発に反対する大集会を開催し,まさに住民同士が対立する状態が続いていた。しかし1973年以降の石油ショックによって企業誘致が進まなくなると,1983年12月に当時の中曽根首相が「青森を原子力のメッカに」と発言し,1984年1月には電気事業連合会(以下電事連)が核燃料サイクル基地の建設構想を公表するなどしている。
このような状況で開催された第9回会合(1984年2月)で,日本原燃サービス(日本原燃の前身)の担当者が説明した「大型再処理工場の基本構想」は,驚くべき事実を明らかにしている。それによれば「本構想は原燃サービス(株)において計画中の第二再処理工場を念頭に置いたものであり,審議のベースとしたものである」,「大型再処理工場の規模は,年間燃料処理能力1200t/年程度」,「使用済み燃料貯蔵容量は3000tとし,その他のレイアウトは3000t分の増設が可能とする」,「燃料の種類は,BWR,PWR燃料(MOX燃料もあり得る。)」というものである。六ヶ所再処理工場の処理能力は,現在年間800tに縮小されているが,使用済み燃料の貯蔵量については3000t(プール1基1000t×3),さらに3000t分の増設が可能になるよう,燃料プールにはその入り口(燃料移送水路の上側の口)がすでに設置済みである(図7)。当時の原燃サービスは,燃料プールの容量を6000tとする構想を計画当初からもち,工場建設の際にもそのための設計を行っていたのである。
さらに放射性廃棄物仕様として,「当再処理工場からの廃棄物最終形態は全て固体とする(但し,クリプトン,トリチウムを回収する場合は,別途検討)」として,クリプトン,トリチウムの回収設備に関しても検討していたにもかかわらず,結局,経済的理由から回収を放棄したことが青森県議会へ提出された資料などから明らかになっている。
1984年4月,電事連は青森県に「核燃料サイクル基地」立地協力を要請し,そして7月には「六ヶ所村」に対して正式に立地協力要請を行う。六ヶ所再処理工場建設への布石が打たれる中で開催された第12回再処理施設小委員会(1984年9月)では,それに呼応するような議論が進められていた。議事概要によれば,(指針)作成にあたって,一般的に再処理施設を対象に記述するのか大型商業再処理工場(筆者注:六ヶ所再処理工場)を対象とするかについては,「大型商業再処理工場を強く念頭において」作業を進めることとなった,と記されている。そして文章の下に手書きで,「下北――800トンを意味する」と明記されている。
この時点で,青森県や六ヶ所村は「核燃料サイクル基地」の受け入れを決定していたわけではない。青森県議会全員協議会が受け入れを決定したのは,1985年4月である。ところが第二再処理工場のための「再処理指針」を策定する政府の会合では,すでに地元受け入れ決定の1年も前から「下北――800トン」として,六ヶ所村での立地を前提に「再処理指針」を策定する方針が確認されているのである。
このような施設の立地点を想定して「指針」を作成するのは,原子力発電所と違い再処理工場が「1点もの」だからというメモもある。核燃料安全基準専門部会が当初考えていた再処理小委の審議方針では,「本来指針とは,複数施設の共通性確保も1つの目的としている事」などを考慮していたが,1985年1月の第14回再処理施設小委員会でも,さらに「下北」に特化した指針をめざす方向が打ち出されている。指針のまえがきについても,「高速増殖炉の再処理施設については施設の規模が小さいので,軽水炉の再処理施設と同列に取り扱うのは疑問であり,対象外としてはどうか。今回は,下北の大型商業施設に範囲を限って検討することとし」,「東海再処理工場については,指針はバックフィットしないのだからあえて書く必要はない」という意見まで出ている。
1985年4月,青森県と六ヶ所村は核燃料サイクル施設受け入れを表明した。同年6月に開催された(指針案)起草ワーキンググループの第1回会合でも,適用範囲は「下北」に限定したほうが書きやすい,という意見が委員から出ている。安全確保の基準である「指針」が,科学的,客観的検討に基づかず特定の地域や条件を念頭に作成されたのである。「再処理施設安全審査指針」は,原子力安全委員会によって1986年に決定されたが,実態は「六ヶ所再処理施設安全審査指針」であった。現行の「新規制基準」が旧「指針」を踏襲していることは言うまでもない。
再処理は電力会社の義務?
原子炉等規制法(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)では,原子力発電所の設置の許可について,事業者が「申請書」を政府に届けて許可を受けることを定めている。その「原子炉設置許可申請書」に記載するべきポイントとして原子炉の型式,所在地など十の項目が規定されている。その中に,「八使用済燃料の処分の方法」という項目があり,原子炉を設置する場合,そこで発生する使用済み燃料の処分方法を記載することが義務づけられている。電力会社は,これによって再処理義務づけの根拠としている(九,十は,2013年7月の改正で追加された)。使用済み燃料の「全量再処理」を建前としているので,どの再処理工場で再処理するのか,工場名が記載されてきた。当初は,セラフィールド再処理工場,ラ・アーグ再処理工場,東海再処理工場などの名前が記され,そして六ヶ所再処理工場へと続いていた。しかし,六ヶ所工場は着工以来約20年,操業延期を19回も繰り返し,各電力の契約量も一杯になってきて,第二再処理工場のめどもない,という状況になったため,ついに最近の設置許可申請では再処理工場の名前が書けない事態となっている。そこで事業者と政府(旧原子力安全・保安院)は,苦肉の策を考え出した。たとえばいちばん最近,2009年に設置許可申請が出された上関原子力発電所(中国電力)の場合は以下の通りである。
「八,使用済み燃料の処分の方法使用済み燃料は,国内の再処理事業者において再処理を行うことを原則とし,再処理されるまでの間,適切に貯蔵・管理する。
再処理の委託先の確定は,燃料の炉内装荷前までに行い,政府の確認を受けることとする。
ただし,燃料の炉内装荷前までに使用済み燃料の貯蔵・管理について政府の確認を受けた場合,再処理の委託先については,搬出前までに政府の確認を受けることとする。
海外において,再処理を行う場合は,これによって得られるプルトニウムは,国内に持ち帰ることとする。
また,再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときには,政府の承認を受けることとする。」(『上関原子力発電所原子炉設置許可申請書』平成21年12月8日中国電力)
もう「何でもあり」の状態である。使用済み燃料はサイト内貯蔵もあり,再処理する場合も燃料の炉内装荷前まで,さらに搬出前までに確認,そして何と海外委託再処理の可能性まであるとしている。つまり事業者自身が,使用済み燃料対策は何も決まっていない,と事実上言っているようなものだ。そして政府も「先のことはわからなくてもOK」としている。「核燃料サイクル推進」,全量再処理という建前をいくら並べてみても,再処理できない使用済み燃料の存在はもはや隠しようがなく,サイクル政策が破綻していることを,事実上政府も認めている。廃棄物問題を先送りしたまま,建設だけを優先させてきたのが原発の歴史だ。
Copyright ©核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団 All rights reserved.
